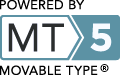「限界集落」は本当に限界なのか。
山下祐介著の「限界集落の真実-過疎の村は消えるか?」を読了。
著者の山下准教授とは、僕が30歳の時、弘前大学の修士課程を履修していたときに初めてお会いしたのだけど、当時「行政法」の教官に指導を仰ぎつつも、実際は「地域社会学」を専攻とする山下准教授はじめ他の教官から伺うお話や講義の方が正直言ってとても興味深く、修士論文を一生懸命作成する傍らで、他の院生の方々と一緒に山下准教授のフィールドワークのお手伝いもさせて頂いた。
僕がお手伝いをしたのは旧中津軽郡相馬村(現・弘前市)に赴いて行った「津軽選挙」の検証。これがまた非常に面白く、地元住民のライフヒストリーの聞き取りなどを経て、僕が修士課程を終えた後になってようやくその内容がレポートとしてまとめられ(まとめるまで紆余曲折があり、時間がかかってしまった)、その後学会でも発表するとかなりの好反応があり、最終的には他の論文と合わせて書籍という形でまとめ上げられた。
(↓本書の参考文献としても登場している。)
その後も「津軽学」や「白神学」の編纂編集に深く携わった山下准教授、首都大学東京へ転任されたことを機に細々と続いていたご縁が途切れかけているのだけれど(山下先生、元気かな。笑)、その准教授が今回発表した書籍のテーマが、「限界集落」。
昭和の市町村合併、そして平成の大合併を経て、「過疎」から「限界集落」という言葉がクローズアップされるようになった。
平成の大合併の際に問題視されていたのが、「行政サービスの均一化」だった。同一行政区域にありながら、同じサービスを受けられないのではないかという懸念はとりわけ、対等とはいいながらも事実上吸収される側の自治体から多く上がっていたように記憶している。
実際、合併という大風呂敷で一括りにされてみると、喉元過ぎれば熱さを忘れるではないが、やはり役所に近い周縁より末端にある地区に対する行政サービスは低下し、「元の役場があった方がまだ良かった」という不満の声は、複数の地域から上がったようだ。そして、整備の行き届かない、いわゆる末端の末端にあるような限界集落と呼ばれる地域は、他の地域とまとまった方がよいのではないか、という極論まで上がるようになってしまったのだ。
さて、「限界集落」と聞いて、皆さんは何を想像するだろうか。
限界集落(げんかい しゅうらく)とは、過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者になって冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落を指す、日本における概念。(Wikipediaより)
...車で行くことすらままならない山間の集落。点在する家々は主を失ったまま荒廃し、細々とこの地で生活を営む腰の曲がった老婆が、意味もなく庭で火を焚いている。傾きかけた平屋の家の中を覗き込むと、2週間に一度やってくる医師の問診だけを心待ちにする爺さんが床に伏している。行政の手も行き届かないこの地域に暮らす最後の老夫婦。この二人がいなくなると、この集落からは人がいなくなり、廃墟だけが残ることに...。
どうだろう、「限界集落」と聞いたときの皆さんのイメージというのは、極端かも知れないがこんな感じではないだろうか。
青森県には、傍目からすると「限界集落」と呼ばれて不思議ではない地区が複数点在する。僕の住む弘前市の自宅から車で20~30分も走れば、本書にも登場する旧相馬村に行くことができるし、亡父が生まれた中津軽郡西目屋村に行けば、「定義上」の限界集落が複数存在する。
しかし、本書でも述べられているとおり、ではその集落がここ数年以内に消滅するかと言われれば、それはあり得ないだろう。
そこに住む人たちが生き甲斐を見いだし、(都会では味わうことができないであろう)そこで暮らすことへの優越感、更にはその次代がその地域への帰属意識を持ち続けている以上、その集落・地域が消えることはないと考える。
なぜそう言えるかは、本書を読み解いていくと明らかになると思う。
ところで、なぜ「限界集落」という言葉が注目を集めるようになったのか。それは、都会から見た地方に対する「偏見」のようなものなのではないだろうか。
個人的には、1990年代に提唱された「限界集落」という、衝撃的な印象を与えかねない言葉が一人歩きし、それが色んな形で歪曲されて、誤った概念で伝えられているのではないかと思っている。
もっとも、40年以上青森県を出て暮らしたことのない僕がこんなことを言うのも変な話だが、都会の方がよほど「限界」に達しているのではないか。誰にも看取られぬままこの世を去り、数か月後に発見されるというニュースが幾度となく報じられたが、こういった方々が発見されるのは、田舎ではなく都会ではないか。
そして、こういったニュースが立て続けに報じられたのは、ある地域でこのような事象が発生した際、他の行政機関が「うちの管轄ではそんなことはないだろう」と、それまで行き届かなかったところまで目を向けた結果として、複数の事象が出てきたのではないか、そんな穿った見方をしてしまう。
地方都市の周縁集落を「限界集落」と揶揄するのであれば、都会の片隅には、地域社会との接点すら損なわれた人たちが生活する「限界コミュニティ」が不特定多数存在しているのではないか。
山下准教授は、フィールドワークとして「限界集落」と言われる複数の現地に赴いて、その地に定住し生活を営む人たちの声に耳を傾けている。
だからこそ本書には、「限界集落」と言われている地域の現在と未来が詰まっており、「限界集落」の真実を伝えていることは間違いない。
田舎暮らしに辟易し、都会暮らしに憧れる人たちに、更に、地方を「田舎だ」と見下す都会暮らしの方々に、そして、田舎暮らしに誇りを持つ人たちに、是非読んで欲しい一冊。