春眠、暁を覚えず
僕はひどく疲れていた。
それは、急に思い立って自宅から岩木山神社までの往復約25キロを走破したとか、家の周りに積もった、3メートル近い高さの雪を一気に片付けたとか、朝が来るまでずっと酒を煽っていたとか、そんな安易な理由ではない。
多分ここ最近の僕は、人と接することに疲れていたのだ。
事の発端は4か月前まで遡る。
仕事の関係で僕は、とある法人の担当となった。
その法人の担当者は、小太りで、いつも腹の周りの肉がベルトに食い込んでいた。奇妙に浮き出た腹の周りの肉は、まるでバウムクーヘンのようだったので、僕は陰で彼のことを「バウムくん」と呼んでいた。
バウムくんは、こちらの言うことに対して何でも素直に「はい。はい。」と答えていたが、それは裏を返せば、我々の知ったことではないので、あとはお任せしますという、どこか他力本願のような生返事にも聞こえた。
かと思えば急に意固地になって、頑としてこちらの言うことに耳を傾けなくなったり、ちょっと面倒なタイプの人だったのだ。
バウムくんを含め、その法人の複数の関係者とは、メールや電話でのやりとりを何度も繰り返し、ようやく頂上が見えてきたところで、僕は致命的なミスを発見した。
例えて言うならばそれは、海水浴にやって来た泳ぎの不得意な大人が、浮き輪ではなくスタッドレスタイヤを手に海に飛び込んだ、そんな致命的なミスだった。
「頼みます、何とかしてくれませんか。」
僕は生返事を繰り返してきたバウムくんから初めて懇願されたが、とても僕一人の手に負えるような内容ではなかった。
しかしながら僕以外、手をさしのべる人はいなかった。仕方なく僕は、バウムくんを始めとする彼らが助けを待つ大海に救助用の浮き輪を放り投げた。
それも人数を遙かに超える量を、幾つも幾つも。
でも、彼らはその浮き輪にしがみつくどころか、手にしていた鋭利な刃物で片っ端から穴を開けていった。我々が欲しいのは浮き輪じゃなくて、ボートなんだよ。といわんばかりに。
例えて言うならば、こんな感じだ。
これには、さすがの僕もキレた。
午前10時42分。執務室。
「今回の件については、こちらの助言に耳を貸すことなく勝手に作業を進められているようですが、それはこちらとしても本意ではありません。このままでは予定に間に合わないこと必至ですが、それでも構わないんですか?」
僕は、電話の向こうのバウムくんにこれ以上ないぐらいの口調で激しく詰問した。
しかしバウムくんは相変わらずの調子で、「そうですか、まあ、何とかよろしくお願いしますよ。えへへ。」と、まるで意に介さなかった。
それでも不思議なもので、この世の中はいざとなれば何とかなるものなのだ。いや、それは僕が今まで、厭世観を抱きつつも、のらりくらりとやり過ごしてきた一つの方法に過ぎないだけなのかも知れない。結局上司に報告相談するまでもなく、事態は一定の収束の方向へと進んでいった。肝心な部分は、完全に棚上げ状態になっていたが。
「やれやれ。いつもこんなもんか。」と、僕は口に出さずにつぶやいた。
狐につままれたような感覚と、デジャヴにも似た感覚。
しかしその感覚は、僕の意識を朦朧とさせつつあった。夢と現実との狭間にある古びた茶色の扉を、僕は何度も行き来している。僕は、その扉を開けては閉め、また開けては閉め、猿のマスターベーションにも似た無駄で無意味な反復運動をただ黙々と繰り返している。
その反復運動でひどく腹を空かせた僕は、相変わらず浮き輪を大海に放り投げるという仕事を進めながら、休憩時間がやって来るのをじっと待っていた。
午前11時58分。執務室。
どこか癖のある、見るからに偏屈そうなその老人は、突然職場にやって来た。
そして、すぐそばにいた職員を捕まえて、僕に会わせろと言い始めた。
今の仕事に取り組むようになってから、僕は短期間で数百人の方々と名刺交換をした。残念ながらその場限りで繋がりが途絶えた人もいれば、その後ずっとご縁が続いている人もいる。
その老人については、確か以前一度名刺交換をしたことがあったような気がするが、できることであればその場限りで繋がりを断ち切りたいような雰囲気を持った人だった。
「ちょっと、よろしいですか。以前一度お話を伺っているんですがね。ひひひ。」
特徴のある独特な訛りと卑屈な笑い声を聞いて、混線していた回路が繋がった。
誰に勧められたわけでもないのに、打合せスペースにある酷く汚れた青い椅子に腰掛けた老人は、もう一度僕に向かって言った。
「ちょっとよろしいですか。お昼なのに、すいませんね。ひひひ。」
老人がまた笑い声を上げる。それを聞いた途端、僕は、虫酸が走る思いに駆られた。
しかし、その老人からロックオンされた僕以外に相手をする人がいるはずもなく、仕方なく僕は、その老人の向かいの椅子に、浅く腰掛けた。
僕の胃の中では、食べ物に飢えた虫たちが、グーグーと鳴き声を上げている。
そして、そんなこちらの事情とはお構いなしに、老人は一人で勝手に話を進めている。
「...で、私はどうすればいいんでしょうね。」
老人は突然、僕に意見を求めてきた。僕の思考回路は、その老人から既に離れていたのだが、断片的に耳で拾っていた老人の言葉を咀嚼しながら、かなり早口で僕なりの意見を述べた。
その意見が的を射たのかどうかはわからないが、老人はちょっと困ったような表情を浮かべながら、「そうですか...。わかりました。」と言った。
やれやれ、僕は何でこんな退屈な話に付き合わなければならないんだろう。
「ところで。」
また老人が切り出した。
「もうお昼休みですね。どこかで一緒に昼食でも、いかがですか。続きの話をしたいんですが。」
冗談じゃない。あなたの話を聞いているだけで、僕の気分は闇にも似た青色になっているのに。
今日はもう、これ以上僕に関わらないでくれないだろうか。
「お誘いはありがたいのですが、これから先約がありまして...。」
しばらく手入れを忘れた鼻の穴からは、無数の鼻毛が伸び放題になっていた。赤黒く皺の寄った皮膚、血走った目、深く刻まれた眼下の隈、どこのお国言葉なのか区別が付かない独特の訛り...もはやこの老人の全てを、僕の五感は受け容れがたいものとして認識していた。
「そうですか。それは残念ですなぁ...。」
「すいません。」
「じゃあ、私はこれで。お邪魔しました。」
「いえ...。」
挨拶もそこそこに席に戻る。老人はこちらに向かって深く一礼して、廊下へと出て行った。
12時27分。執務室。
胃の中では、虫どもが更に重層のコーラスとハーモニーを奏でながら大合唱している。三流の歌手のバックコーラスなら、充分に務まりそうだし、町内のカラオケ 大会なら、入賞確実かも知れない。一刻も早くその合唱を止めるため、僕はロッカーから毎日持参している手弁当を机の上に置いた。
先約なんて、真っ赤なウソだった。
お昼休みという自由な時間を、もはや受け容れを拒絶している一期一会の老人とともに過ごすということ自体、僕にとっては耐え難いことだったのだ。
給湯室に向かうため、袋に入った粉末状のコーンスープとマグカップを手に、廊下に出たその時だった。
「お昼ですか...。そうですか。残念ですね。ヒヒヒ。」
先ほど帰ったはずの老人が、廊下に張り出された職場の席図を眺めつつ、横目でこちらを見やっていた。
悪寒が走った。老人は、その後の僕の行動を監視していたのだ。
老人に声を掛けられた僕は、動揺を隠しつつ「失礼。」と声を絞り出すのがやっとだった。
小走りで給湯室に向かい、乱れた息を整える。
95度の熱湯をカップスープにゆっくり注ぎながら、動揺が鎮まるのを待った。スープの中のクルトンが、押し出されたように浮かんでくる。胃の中の大合唱は、僕の様子を窺うようにピタリと止んでいた。
やれやれ、一体今日はどうなっているんだ?
恐る恐る廊下に出てみる。老人の姿は、既になかった。
職場に戻り、いつもより30分遅れの昼食を取る。冷めきった揚げ物に塩気のない焼鮭、白米と卵焼きを交互に口に運ぶが、嗅覚や味覚はまるで働いていなかった。結局僕はそれらを頬張っては、スープで一気に流し込んだ。
午後12時45分。執務室。
残り15分となった休憩時間を、僕は仮眠に充てた。仮眠とはいいながら、僕はここ数か月では記憶にないぐらい、熟睡していた。
「マカさん、マカさん...。」
誰かが僕を呼んでいる。
ゆっくりと目を覚ますと、既に午後の勤務が始まっていた。
僕を呼び起こしたのは、隣に座る女性だった。
「大丈夫ですか?何か具合が悪そうですよ。」
「いや、大丈夫だよ...。」
「本当に大丈夫ですか?何か凄く具合が悪そう。午前中と全然様子が違うんですけど...。」
「ありがとう。本当に大丈夫だから。」
午後1時08分。洗面所。
まだ眠気が抜けないまま洗面所に向かい、鏡に映った顔を見て、僕は「あっ!」と声を発した。
顔は真っ赤に紅潮し、目の下には隈が浮き出ている。
そしてそれは、僕が激しく嫌悪感を抱いた、あの老人の特徴と酷似していたのだ。
僕は、クリーニングしたばかりのスーツが濡れることも構わず、冷水で顔を洗った。ただひたすら、顔を洗った。
しかし、状況は何も変わらなかった。
僕は、誰だ?あなたは、何者なんだ?
午後1時14分。廊下。
事態を飲み込めぬまま僕は洗面所を出て、廊下に立ち尽くした。
思わずあの老人の姿を探したが、そこには誰一人として人はおらず、静まりかえっていた。
廊下を挟んだ両側にある各執務室の明かりは消え、人影が感じられない。まるで廃墟に迷い込んだような雰囲気だ。
ふらふらと正面玄関に向かうが、玄関は閉ざされ、暗闇の様相を呈している。それは、どこかで見覚えのある、闇にも似た青色...。
普段常駐しているはずの受付には誰も人がいない。
その時、突然受付に置かれた電話が呼び出しの音を鳴らした。10回、20回...恐らく誰かが受話器を上げるまで鳴り続けることだろう。でも、周囲を見ても、そこには僕しかいない。仕方がないので、受話器を取り上げてそっと耳に当てた。
「もしもし?」
「...お昼休みはいかがでしたか?ヒヒヒ。」
背筋に無数の氷が詰め込まれる感覚を覚えた。あの老人の声だ。
「何なんですか?一体?僕に何の用件ですか!?」
「そう怒らないでくださいよ。大した用事じゃないことはあなたも知っているはずだ。でもその大したことない用事は、我々にとって死活問題なんです。」
「だから、僕にどうしろというんだ?」思わず声を荒げた。
「答えは簡単ですよ。それは、あなたが一番よくおわかりのはずですから。ヒヒヒ。」
「...。」
「また電話しますから。では。」
一方的に切られた受話器を手に、僕は茫然と立ち尽くしていた。
やれやれ。一体、何が起きているんだ?
受話器を置いた途端、再び電話が鳴った。間髪入れることなく、僕はその受話器を手にした。
「もしもし。もしもし!」
「...いつもお世話になっております。えへへ。」
今度はバウムくんの声だ!
「何だ!僕に一体何の用だ!」
「まあまあ、そう怒りなさるなって。何の用って、あなたが一番わかっているじゃないですか。えへへ。」
...さっきの老人と同じようなことを言っている、と咄嗟に僕は思った。
「また電話しますから。じゃあ、失礼します。えへへ。」
...?
!!!
午後12時57分。執務室。
ハッと夢から覚めた。脳内に形成されたイメージが、カラカラと崩れていくのがわかった。
そこにある光景は、普段と何も変わらない、いつもの日常の光景だった。
どうやら僕は、村上春樹に相当感化され過ぎたようだ。
でもきっと、村上春樹の新作はこんな感じなんだろうと思いを馳せながら、「やれやれ。いつもこんなもんか。」と、僕は口に出さずにつぶやいた。
(このお話は、フィクションとノンフィクションが入り交じっています。)





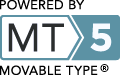
コメントする